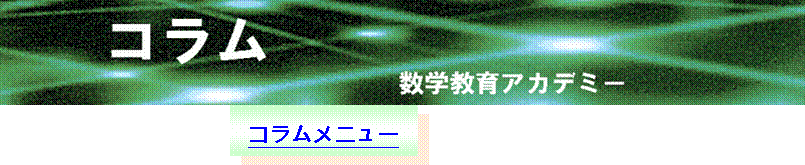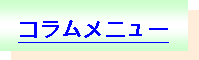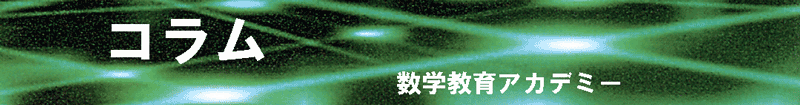
|
T O
P | 基本理念 | コ
ラ ム
| 教 材
| Q & A
| お問い合わせ 算数・数学 22. 板倉聖宣先生との出会い 今年の春に初めて板倉聖宣先生のお話を直接拝聴する機会を得ました。 そして、思ったのは、もっと早く出会っていたらよかった、という後悔のような思いです。 私が大学を出て教育者を目指したころ、私の従兄弟が板倉聖宣先生の『科学と仮説』という本をわざわざ送ってくれました。彼は「これはすごいから是非読むといい」と絶賛していました。私は、早速読んで真実の響きを感じたものの、自分が教えるのは数学であり、「数学には仮説実験授業は直接は使えない」と思って、あまり深入りしなかったのでした。それからあっという間に時は経ったのでした。10年を「ひとむかし」と呼ぶなら「ふたむかし」以上の時が。失礼なことですが、私は板倉先生という方はもう疾うに過去の人になっているものと思っていました。しかし、とんでもない。目の前で、にこやかに講演をされています。パッと見たところどこにでもいるおじいちゃんです。ところが。ところが。 本当にすごかった。そして、私はグイグイと板倉ワールドに引き込まれていきました。 私は、目が覚めるようにうれしかった。感動でした。 そこの思いについて書きたいと思います。 長年教育関係の仕事をやっていると、それまで見えなかったいやなものが見えるようになってしまいます。何かといえば、「不純な教師世界」とでもいいましょうか。なんら官僚や政治家の世界と変わらない醜い欲がうごめいている世界です。若いころは純粋に子供たちとの関わりに情熱を燃やしていたでしょう。教師は。しかし、途中からどうもおかしい。話が通じなくなっていくのです。そして、彼が管理職試験に挑戦していたことが後からわかります。 「試練を引き受け、自分が教育の世界に道を開くための捨石となろう」というような気概があるのなら問題ないのですが、そうではなく、「楽をしたい」、「人の上に立ちたい」という欲だけで管理職を目指すため、この世界すべてが、不純なものを中心にして動いていくようになってしまうのです。 たとえば、研究会をしても、形としての見栄えだけを気にします。残念ながら「王様は裸じゃないか」と声を上げる純粋無垢な智慧を持った「子供」はほとんどいませんし、いてもその声は消されてしまいます。中身なく空洞化した魔物。まさに、江戸時代末期の徳川幕府の官僚と同じ姿です。勝海舟や吉田松陰のような人はいない。 こんな冬枯れの野のような中で、私は教育界には絶望していた矢先だったのでした。 板倉先生は静かに語ります。実験なども見せながら物柔らかに語っていかれます。驚くのは、ほんとうに柔らかなのにいつの間にかそのお話の中に引き込まれてしまっている私がいることです。それは、ただ仮説実験的に講義を進められるから、というのではありません。 一言で言えば、 真実の響き とでもいえましょうか。ただのおじいちゃんに見える板倉先生のお話を聴いているうちに、その眼が鋭く、透明に輝いていることに、思わずハッとします。これも、真実の響きです。音声、眼光、想念、話される内容、すべてが、「真実」という波動を放っています。そして、そこにこちらの周波数を合わせると、実に気持ちのよい感覚になるのです こう書くと、板倉先生をご存じない方は、「何を大げさなことを」と思われるかもしれません。 しかし、私は、何も大げさなことではない、ごく普通のことだと実は思っています。 けれども、自分をチューニングして周波数をそこに合わせることができる人でなければ、たとえどれだけ見ても聴いても、またその場に何回居合わせようとも、わからないでしょう。出世街道まっしぐら(現在あるいはこれから)の人にはわからないでしょう。 板倉先生は、ずっと何十年間も、真実を大切にする生き方を瞬間瞬間してこられたのでしょう。それは、自分の内なる声にうそをつかない生き方ということです。 私は、このような方が教育の世界におられたということ、そして知ることができたということで救われました。 『汝ら、狭き門より入れ。』とはマタイ伝の言葉ですが、まさにこの狭き門は自分自身をスリムにしなければ通れません。たとえば、出世欲を心に持っていながら同時に通れる門ではないのです。 本当に大切なもののみを残し、大切でないものは捨ててしまってできるだけ簡素にならなければ、通ることはできません。 仮説実験授業そのものについては、ここでは立ち入りません。 しかし、まさにその核となるのは、《リラックス》であり、子供から無限の力を引き出す可能性を持った、まさに21世紀の教育だといえるでしょう。 課題ももちろんありますが、これまで何十年というスパンで実践され積み上げられた財産の大きさには眼を見張るものがあります。今後も、次々と課題が解決されて財産はより高く積み上げられるでしょう。そして、更なる高次の課題が現れてますます高みに登っていくことができるでしょう。 ただ、そのためにもあえて苦言をひとつだけ呈するならば、会員の方々に対してです。 今現在板倉先生が頂点にいてくださるから、常に仮説実験研究会(?)そのものが自ら自分自身を壊してまた創り直していく、という創造の歩みをしていられるのです。板倉先生のまなざしがあるからこそ、なのです。ここのところを忘れてはいけません。 先ほど述べた「狭き門」は、出世欲ももちろんですが、名誉欲があっても通ることはできません。これらは、傲慢さにつながります。 1冊の《授業書》を創り出すということがどれほど壮大な事業であるか、それをきちんと認識していれば、傲慢さは絶対にかけらほども出すことはできません。 どうも、《授業書》の作成者の多くは「天狗」になってしまう傾向があるようです。 そこのところを、厳しく自戒しましょう。 今後何十年も、板倉先生のご意思を継いでいけるように。これまで築き上げた財産を水疱に帰してしまうことがないように。 ほかのどの組織にもない優れた組織であるが故の、苦言でした。 身近にいる愛するものには、心を開いて、あえて言いにくいことを言うことも大切です。 この苦言については、今後もう少し具体的に書くことがあるかもしれません。 |
|||
|
・
|