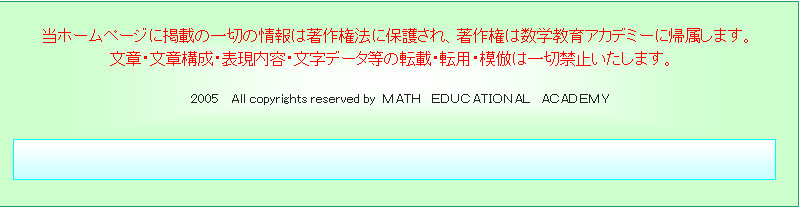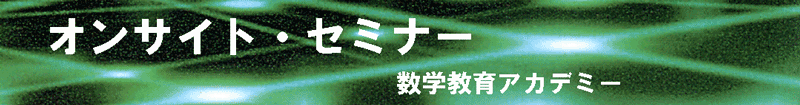
SRS THE SUPER RELAX STUDY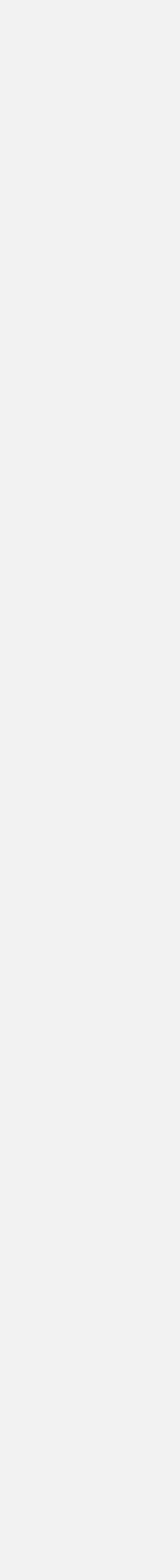
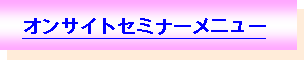
TOP>オンサイトセミナー
S01. 教育の再生に向けて
|
現在、子供を取り巻く環境はこれまでになかったほど酷く、その崩壊の速さには恐るべきものがあります。それは、もはや、学校や教育機関だけで手を打てるような生易しいものではありません。社会のすべての大人たちが、「本気でこの国のことを考えよ」と呼びかけられているようです。 呼びかけられている…? どこから? どこからかは私にも分かりませんが、どこか見えない次元から呼びかけが響いていることは確かです。 今本当に問題なのは、これだけ明確に呼びかけが聞こえているにもかかわらず、誰もその呼びかけを聴こうとせず、また本当にそれを聴ける心を持った人も少ないということです。 けれども、この呼びかけを聴き、吸い込める人が増えれば増えるほど、何かが変わります。 そのような気持ちで、オン・サイト セミナーの第1を発信します。 |
|
教育の再生に向けて |
![]()
|
教育の再生に向けて (1) 「いびつな格差」の行き着く先 学校の教科の勉強は、いったい何を目指しているのだろうか? 小学校と中学校とでは、その色彩は大いに異なるだろう。都会と田舎でも異なるだろう。 「受験」があるからである。「受験」の合否はその子供の人生の道に大きく影響するのだから、決して無視することはできない。公立学校、私立学校、塾、予備校などが複雑に絡み合って、今の教育界を形成している。 教育界にあって一番大切とされているものはなんだろうか? 私立学校、塾、予備校の先生にとっては、「経営」だろう。正直なところ、そうであろう。生活していかなければならないのだから。生徒が来てくれなければ「経営」はなりたたないのである。そして、生徒に来てもらうためには、親を味方につけなければならない。 では、親の関心はどこを向いているか? 「進学」である。「いいところ」に進学できることである。そこで、「名門校」に多く合格者を出しているところを探すようになる。先生の側もそのニーズにこたえなければならない。その点において、指導要領のしがらみから自由な私立学校や予備校は、公立学校に対して大いに優越感を持ちながら、このレールをより速く進んでいく。 ところが最近は、小中一貫校や中高一貫校がどんどん新設されて、公立学校の中においても、「格差」が拡大している。義務教育においても、「受験能力の高い」子供は校区を越えて「いい学校」に集まるようになる。 感受性豊かな柔らかな時期にすでに機械仕掛けの受験勉強によって人間性をいびつにしてしまうそんな子供が、「優秀な子供」とみなされて、選別されていくのだ。なんということだ。「いびつな格差」が拡大していくのである。 これは、日本の未来を見たときに、ほんとうに嘆かわしいことだ。 ライブドア事件を見ても構造はあきらかであろう。「人の心は金で買える」などととんでもない亡国語を発した堀江氏を時の総理大臣や自民党幹事長が「息子だ」の「弟だ」の言って持ち上げて利用しようとした。しかし、検察の努力と慧眼によって国民は早く目を覚ますことができた。心無き「二極化」すなわち、心無き「格差拡大」の行き着く先は、即滅亡なのである。 もう一度ライブドア事件を振り返るが、あの時検察が行動を起こさなければ、日本では猫もオタマジャクシもネットで株取引をするようになり、汗を流すことを忘れお金で心まで買おうとする蛮行が日常当たり前のこととなり、そして、この日本はローマ帝国が滅んだのよりも早く、「滅亡」していただろう。 もう一度言おう。心無き「格差拡大」の行き着く先は、即滅亡なのである。先日の、少年による自宅放火親兄弟殺し事件は、まさにその象徴である。われわれ日本国民は、他岸の火事として安穏と見るのではなく、われわれが作っているこの社会の縮図があの事件だったんだと襟を正してみるべきなのだ。あの少年一家はあれほどの犠牲を出すことによって重たい試練を背負うことになったが、それはわれわれすべてが実は背負っているものだということである。 |
|
教育の再生のために (2)SOSのサイン 火の光をいっぱいに浴び、水や養分を吸い上げてすくすくと育つ草花。日のあたらぬ寒い北面に育つ竹もあれば、岩場に落ちた種が岩を突き破って茎を伸ばすこともある。 どのような厳しい世界に生まれ育っても、そこから芽を出して育っていく力が人間にはある。この力を助け、将来あるとき美しい花を咲かせることができるように、そんな力を育むのが教育である。 大人が描いた姿に近づけてあげるのが教育なのではなく、一人ひとりがそのうちに秘めた可能性を開花できるように援助すること、これが教育なのである。 したがって、教育のやり方というのは、すべてを教え込んでいくのではなく、もっとも本質的なことひとつを教えて、後はそっとしておくこと。そして、子供たちの内から沸きあがってくる「学びたい」という気持ちを原動力として、子供自らが学びを進めていくこと。そのとき、その学びを深める手助けをすること。これが、教科における教育の方法である。 そこにおいて、何よりも必要なことは、《リラックス》である。 子供が知的欲求を持つことは、人間としてごく自然なことなのであって、おなかがすいたら食べ物を欲するのと同じである。しかし、こと「教科の学習」においては、楽しくおいしく食べるというよりも、まずくて食べることが苦しいのが今の教育である。そんな中では当然、リラックスして楽しくおいしく食べることはできない。両肩に力を入れて大きく息を吸い込んで目をつぶって飲み込まなければならない。学校というものが、教科の学習において、「苦痛」となっている児童生徒はどのくらいいるだろうか? さらに、(「苦痛」とは意識することなく徐々に)自分で自分を殺していっている子供はどのくらいいるのであろうか? 進学校に進んでいた生徒が突然自宅に放火して親を殺す、これは、極端な事件ではあるが、放火したり殺人したりこそしないけれどもその少年と同じどうしようもない閉塞感を持っている子供はかなり大勢いると思われる。 不登校も引きこもりも、子供が抱えている苦しみにおいては同じである。 非行も、発散の仕方は反社会的ではあるが、ひとりひとりが抱える閉塞感はやはり同じである。 虚無感と言ってもいい。 先日起こった、少年による自宅放火事件は単なる独立したひとつの事件なのではなくて、日本中のすべての子供からの「呼びかけ」である。 責任は大人すべてにある。 今の社会を作っているすべての大人である。 単にひとつの学校だけで解決できることではない。ひとつの家庭だけで解決できることではない。ひとつの地域や自治体だけで解決できることではない。 現在、社会も学校も、さまざまなところで崩壊の兆しを見せているが、これは何か内なるものからのSOSのサインであると見ることができる。そう受け止めて、事態を自分の利害を越えてよく見つめ、事態からの呼びかけを受け止めようと耳を傾けていれば必ず聞こえてくる内なる声がある。 まだ、私にも、そのはっきりとした声は聞こえない。 けれども、必ず答えはある。 われわれに必要なのは、志である。「自分を超えてただ事態からの呼びかけを聴こう」というこの志である。 そして、同じ志を持って探求していく仲間を「同士」と呼ぶ。 まだ見ぬ同士の存在を信じて、発信していきたい。 |
|
教育の再生に向けて (3) 教育における人間性破壊 子供にとって、教科の学習において最も大切なことは、「オヤッ?」、「面白そうだ」、「もっと考えてみたい」、「たしかめてみたい」、「本当だろうか」といったような、《興味関心》の刺激である。それが強くなって、「解決したい!」、「何とかして知りたい」という《意欲》となる。 この《意欲》の水がひとたび流れ出すと、もはや自分が主体となって学習を進めていくことができるのである。もちろん発達段階に応じて適切な援助は必要だが、子供は新しい学習内容を知的に理解し、そして難なく使うことができるようになっていく。 この場合、子供にとって、自分の「知りたい」という欲求に対して、学習内容が応えてくれたということが何よりの喜びなのである。そして、その結果自分の世界が広がった喜びもある。 ただし、さらにその結果としてテストでいい点を取るということは、まったく別のことなのである。それは、何かの競技で優秀な成績をとるというのと同じことで、「できるようにするための努力」というものが要請される。これは、まさに強いて勉めなければならない。もちろん先ほどのエネルギー(意欲)の流れができていれば、たやすいことではある。けれども、自分が知りたいと思わないことでも強いて勉めなければならなくなる。そして結果として優秀な成績をとるなどの成果に結びついたときは、それなりの喜びがあろう。だがそこまでいけなかった場合はどうだろうか? 以上、教科の学習について2つのことを書いた。 前者は純粋に学習者(本人)と学習対象との間の関係である。学習者(本人)と学習対象との対話ともいえる。第三者が何らかの手段でその学習を助ける場合も、それは、学習者(本人)と学習対象との対話を助けているのである。(これには、仮説実験授業というものがある。) それに対して後者は、学習者(本人)と学習対象の間に、テストを作る人(採点して順位を出す人)や一緒にテストを受けて自分と比べられる人といった部外者が介入してくる。 入試などは、受験者を選別することを目的としている。無制限に何人でも合格にするのではなく何らかの定員枠が決まっている。したがって、その枠外の人数は切り捨てるのである。 現在日本の教育は、教科の学習において、学習者(本人)と学習対象の間に部外者が介入してくるものに成り下がっている。そうでなければ成り立たないのだ。 唯一、進学を意識しなくてよい「普通の」小学校では、仮説実験授業のような授業ができる。(普通の小学校では小学校を卒業すれば全員が自動的に中学校へ進学するようになるから受験というものを意識しなくていいのだ。田舎では、まだこのようなのどかさが享受できる。) しかし、最終学年で次の進学先を受験によって決めなければならない場合は、悠長なことは言っていられない。受験で点が取れなければならないからだ。 そういうところでは、畢竟、上記後者のような学習のみに重点が置かれるようになる。 具体的にいえば、「意味なんかわからなくていいから、覚えて使えるようにしなさい。応用問題はどんどん出てくるよ。全部覚えてしまいなさい。」こうして、大脳前頭葉は使わせず、いきなり側頭葉(左脳)のみを加熱させていくのだ。 実はこれは恐ろしいことである。人間性破壊と言っていい。 |
|
教育の再生に向けて (4)ゆとり路線の果ての危険な流れ 数年前に文部科学省がそれまで以上に強力なゆとり路線を打ち出して、現場を含め教育界は大混乱した。まずは、それまでよりもずっと忙しくなった学校現場。そして次に、年々低下していく子供の学力。次に、次第に顕著になってくる子供の学力の二極化。 さて、文部科学省は、引っ掻き回しただけでその後なんらの有効な手当てもしなかったので、日本の教育界は、ある方向へ向って暴走し始めた。 その最初の動きは、「百マス計算」である。「百マス計算」はただの「百マス計算」でしかなく、それ以上のものでもなんでもない。ところが、不思議なほど、周囲がこれをもてはやし、本屋にもその関係の本が並び、陰山氏は一躍脚光を浴びた形となった。私などは、アレは何らかの企業の儲け戦略の一環だと思っている。ともかく、「百マス計算」などという面白みのないものがあれほどの脚光を浴びるには、それなりの「需要」があったわけだ。それはまさに、わが子の学力低下を心配する親である。また、児童の学力低下の現実と「学力をつけろ」という《周囲の圧力》とのハザマで、一体どうしたらいいのかわからなくてワラにもすがるつもりでそれをつかもうとした小学校教育関係者である。 小学校の現場も、そこまで「落ちた」。いまや、低学年で足し算の繰上りなどを教えるのに、小学校ではいきなりカードをポケットに入れさせて覚えさせるという。公文以上の恐るべき愚法である。 そして、いまや、小中一貫校や中高一貫校などが私立進学校に対抗しうる公立学校として注目され、そこへの入学を目指してその地域の親は血眼になっている。 これは、何を意味しているのか? これは、ついに日本の公的な義務教育までもが「砂漠化」していっていることを意味しているのだ。「受験競争」は「競争」でしかなく、それを初めから目標に掲げてしまうならば、それはある種の地獄への突入を意味する。 最初に要るものは何か? それは大自然とのふれ合いである。学問とのふれ合いである。ゆったりとしたその時間を持って初めて、その後の受験競争をも正常に乗り越えていくことができるのである。 大自然とのふれ合いも学問とのふれ合いも何もなく、いきなり受験競争に突入して行ったら、人間性は破壊される。 今、日本全体が、システムとしても《二極化》を作り始めている。 そして、世の「熱心な」親たちは、わが子を「勝ち組」に入れようと血眼になっている。 われわれが見抜かなければならないのは、そうした誤った原理とシステムに振り回されたら、その行き着くところに何があるのかということである。 日本の心ある人々は、それをこそ真剣に考えなければならない。 修羅の世界にわが子を突き落とせば、そこには身を八つ裂きにされるような苦しみが待っているのである。 いまや世の中は、ついに少年が自宅に放火して親を殺すところまで行った。「そこまでやらなければ、わかってもらえないの!?」という悲壮な叫びが聞こえる。少年も、自分でそこまではっきりとは意識してはなかったろう。ただ苦しかったのである。 総理大臣は変わったが、教育に関しては月も星もない大昔の夜に匹敵するほど、暗い!一国の首相が教育に関して何の展望も持ってないのである。そして、経済の見かけ上の活性化と同様に何でも二極化してしまえば道は開けるんだ、というくらいの子供だましの論理しか持ってない。闇は深い。 大勢がそのような流れを作っている中で、社会のミクロ構成要素であるわれわれ、子供の教育にかかわる心を持った大人たちは、いったいどうしたらいいのだろうか? それを今こそ真剣に考えなければならない。 |
|
教育の再生に向けて (5)算数・数学教育を通しての人間教育 ① 算数・数学教育において、《教育の再生》を目指してみよう。 同じ「2+3=5」を教えるのでも、人間性を破壊する方向へ行くことも可能だし、人間性を育む方向へ行くことも可能である。 では、算数や数学の教育によって人間性を育むとはどういうことなのだろうか? 本稿『教育の再生に向けて(3)』で少し触れたが、人間性を育むとは、子供の興味関心を刺激し子供自らの学習意欲を引き出してその意欲の流れに乗って世界を広げていくことである。この世界は感動に満ちている。窓の外の山の景色をぼーーっと見ること、そして山にいって見れば谷川のせせらぎの音や鳥の鳴き声、木々のこずえの風に揺れる音、木漏れ日、などなどさまざまなものがあり、一つ一つに不思議があり、そして感動がある。雷が鳴るのを見て、フランクリンは不思議に思い命がけの実験をして電気を見つけ、ベートーベンは田園交響曲のクライマックスにその音を持ってきて自分の苦悩を表した。人間は、大自然の中に出て、何かわからないけれどもすごい「力」と持ったものと交流してきた。それは、自然に降りてくるものである。自分の力をはるかに超えた大いなる力である。そして、それらに対する畏敬の気持ちを人間は忘れなかった。ベートーベンの音楽が百年を超えても、苦しむ人々に希望を与えてくれるように、真善美は私たちに生きる希望を与えてくれる。 ところが。いつからなのだろう? 人間が畏敬の気持ちを忘れて、傲慢になってしまったのは。何でも自分でできると思い、また自分でできることがえらいという社会通念をつくってしまったのは。 数学をそのような気持ちで「使えば」、行き着く先は、原爆である。原爆に象徴される破壊兵器すべてである。 数学を、真善美に触れるもの、ととらえるならば、まったく違った世界が現出する。ドキドキわくわくするように面白く、そして感動的であり、それはまるで美しい曲を聞いたり美しい絵や景色を見たりしたのと同じように心が癒される世界なのである。 残念ながら、そのようにこの世界を歩めた人は少ない。 いつの間にか、岩がごつごつした薄暗い谷に迷い込み、そこから抜け出せずに、朽ち果ててしまった人が多いのだろう。けれども、分数の計算を忘れたからとか、自分は学生時代いつも数学は0点だったからとかいう理由で卑屈になる必要はない。むしろ、そのような人のほうが「正直」である分、真善美に触れるのは早いかもしれない。一流大学へ進んだり、あるいは数学の研究職に就いたりしている学者よりも、早いかもしれない。学者は別の谷に迷い込むのである。名誉欲の谷に。論文を適当に発表して教授や助教授の椅子に安穏として座っている者のほうが、「自分は数学者だ」と思っているだけ始末が悪いかもしれない。 神は一匹の迷える羊にも全心を傾けるという。同じように、数学の女神(?男かもしれない)は、いつも0点ばかり取っている誰かに、まもなく微笑むのかもしれない。 算数・数学教育において人間性を育むためには、今述べた視点を持てることが絶対に必要なのである。 そして、その視点から算数・数学教育に取り組んだとき、《教育の再生》は間違いなくなされるであろう。 |
|
教育の再生に向けて (6)算数・数学教育を通しての人間教育 ② 準 備 中 |